在来工法とツーバイフォー(2)
- ku-kan
- 2021年4月29日
- 読了時間: 2分
前回、在来工法とツーバイフォーの違いについて書きましたが、
「在来工法とツーバイフォーは、どちらの方が優れているのですか?」
とも専門外の方からよく聞かれます。
2つの工法があり、どちらかがなにもかも優れていれば、
やがてもう一方の工法はすたれてしまうでしょう。
在来工法もツーバイフォーも、どちらも一長一短があります。
ツーバイフォーを中心に比較しますと、
一般に在来工法よりも箱型構造体であるツーバイフォーの方が
丈夫だと言われています。
が、前述のように面で構造体をつくっていくので、
本当は壁や床にあまり穴を開けたくない構造です。
しかし実際には窓は欲しいし、
床に階段用の穴がないと上下階の移動ができないので、
どこまで開けていいかという細かい規定があります。
このため間取りによる融通が制限され、
また増改築しにくいのも欠点のひとつです。
在来工法のように梁1本1本サイズが違うのではなく、
壁や床に使う木材のサイズが統一して決まっているので、
各階最も大きい梁せいで階高が決まっていくこともなく、
階高、建物の高さが低く抑えられる一方、
上階の音が下階に伝わりやすいという欠点もあります。
現場に決まった材料を多数搬入すれば、比較的高度な技術は必要とせず、
骨組みが出来上がっていくという利点もあります。
あらかじめある程度工場で床や壁を作って来る
プレハブ工法にも適しています。
面で構造体を組むので、比較的気密性も優れていると言われています。
ただこの材料を現場で見た時に、
在来の木材に比べると、微妙に曲がっていることがあり、
個人的には施工精度に不安が残ったことがありました。
国内ではだいぶ浸透したとはいえ、
まだまだ在来工法と比較すると、
意匠設計者、構造設計者、施工者で慣れた方が少ないのも現実です。
在来工法は骨組みを1~数日で一気に屋根まで組み上げてしまうのに対し、
ツーバイフォー工法は1階床から順々に何日もかけて組み上げるので、
雨天の場合床・内壁まで構造体が濡れてしまうことがあります。
これについてはあらかじめ床にシートを張っておく等の
対策をしている業者が多いです。
在来工法とツーバイフォー
ご自宅を建てるときどちらを選ぶか。
これらのことを少し頭に入れて決めるといいかもしれませんね。



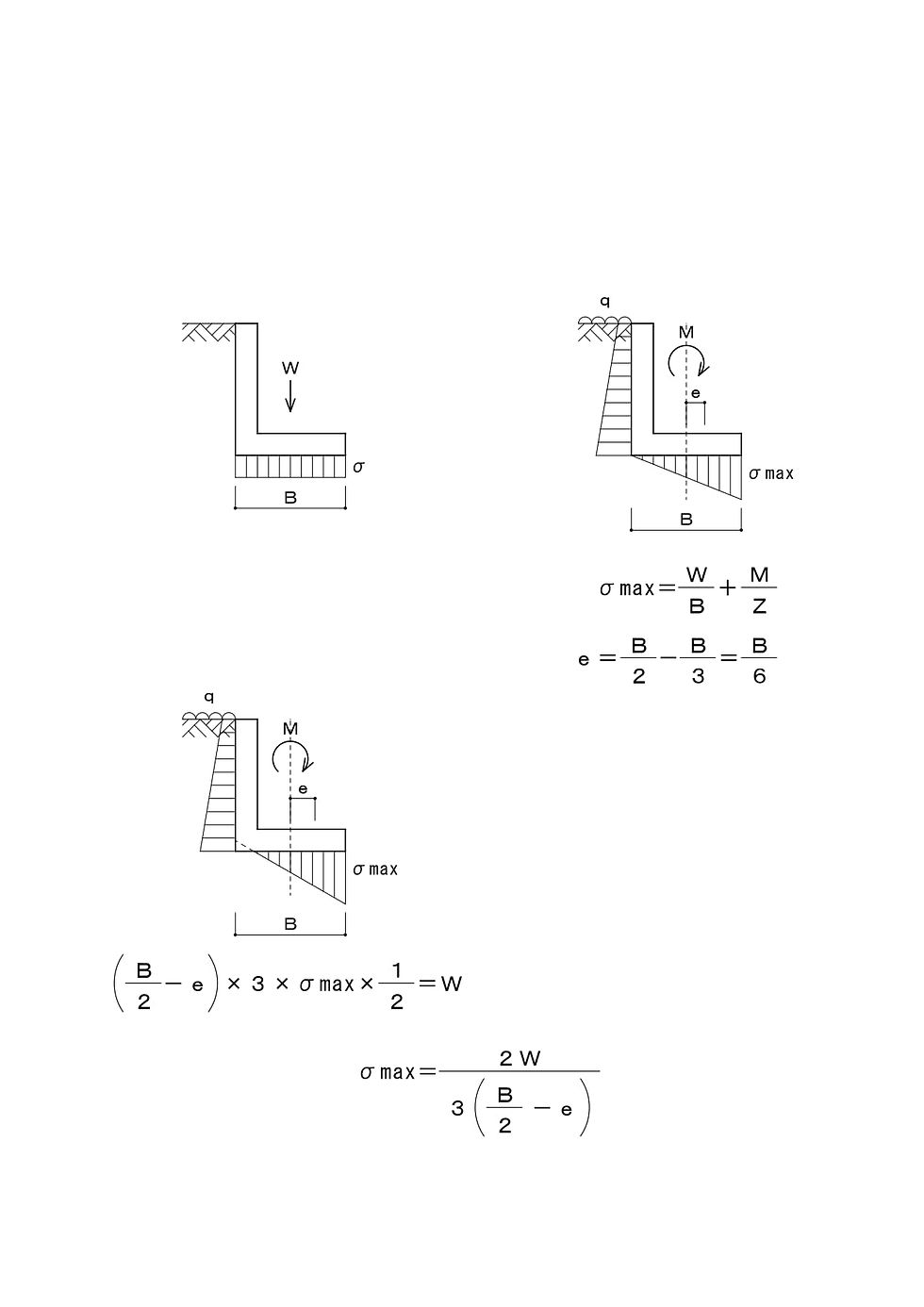


コメント