偏心率の不思議
- ku-kan
- 2022年3月14日
- 読了時間: 1分
更新日:2022年9月12日

建物を各階平面図で見た時、その重さの中心を「重心」(図のG)と呼びます。
地震力が建物を揺らそうとする点とも考えられます。
それに対し木造の場合、地震に耐えるのは耐力壁ですが、
これらの壁の中心を想定すると、これを「剛心」(図のK)と呼びます。
地震力に耐えようとする点とも考えられます。
構造的にはこの2つの点が一致していれば理想なのですが、
これらが離れていると、地震時に建物が平面的にねじれるような動きをして、
部分的により大きな力がかかり、望ましくありません。
この2つの点がどの程度離れているかを表す数値が「偏心率」とよばれるもので、
例えば木造軸組工法であれば偏心率0.3以下にしなければなりません。
建物の南側に大きな窓を取り、北側を壁ばかりにしたような家は、
壁のバランスが悪く、偏心率をクリアできません。
不思議なのは、これまで数多くの建物を構造計算させていただきましたが、
この「偏心率」がいい建物は、意外とすんなり構造計算が終わるのです。
やはりバランスのいい建物は、総じて安全ということでしょうかね。


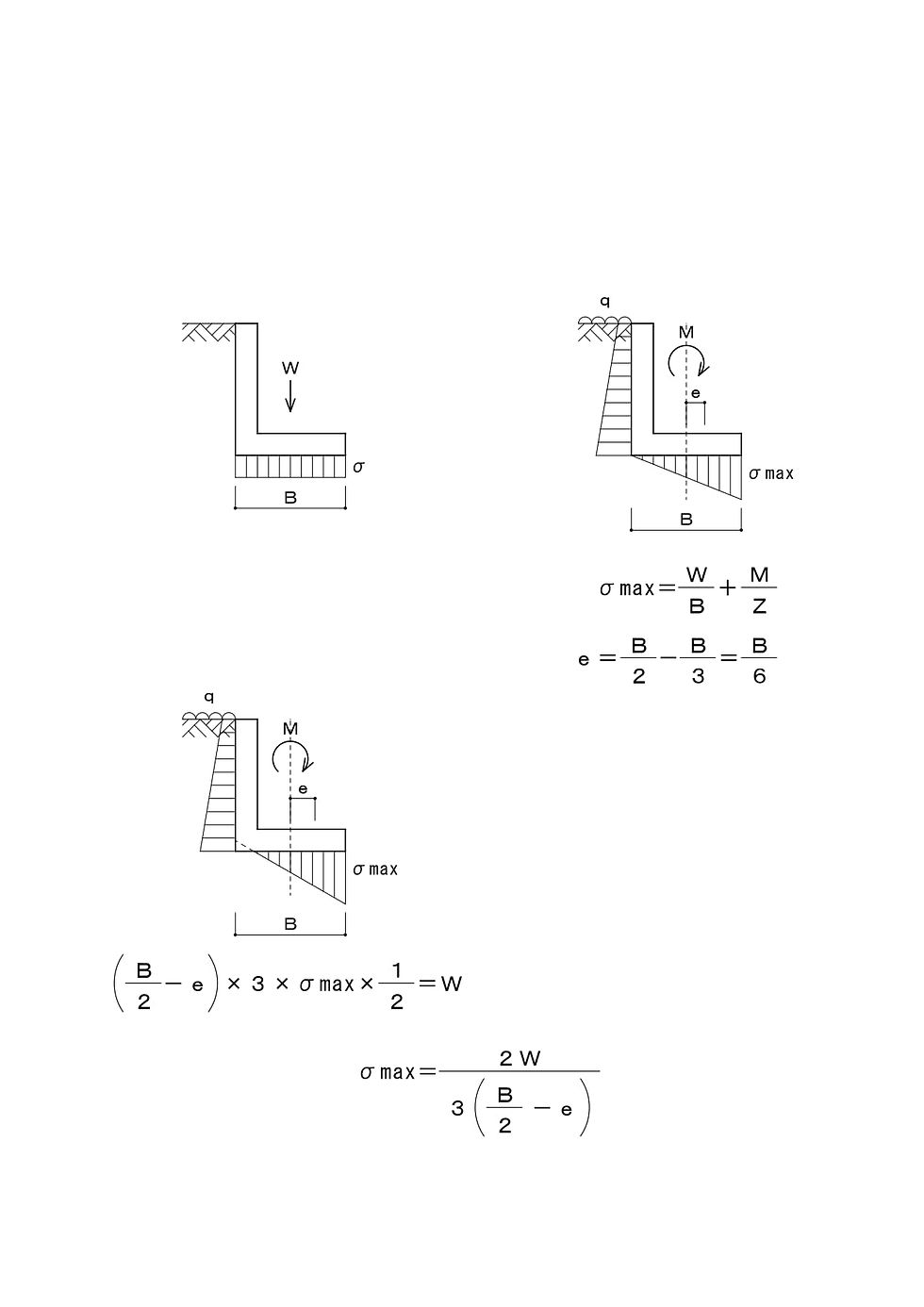


コメント